| 08 | 2025/09 | 10 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
でも、それだけで。
何も変わらない毎日を送っていた。
焦りと不安と、そして僅かな恐怖心を抱きながら。
毎日を、過ごしていた。
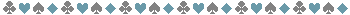
「じゃあ、行ってくるわね。お留守番、宜しくね?」
「ん、行ってらっしゃい、お姉ちゃん。……がんばってね」
見送ってくれた妹の頭を軽くなでて、私は微笑み、家を後にした。
あれから、十年。
私は、母が昔働き、そしてお忍びで遊びにきていた父と出逢った酒場で働いていた。
…あの日、母に言われた通りに。
仕事場の途中までの道で、私はため息をついて空を仰いだ。
"愛しているわ"
母が残したあの言葉。
疑っているわけでは無かった。
信じていた。
恨んでも居ない。
「…だけど」
自然と口から言葉が零れる。
其の一言だけで、留めて。後は心の中で、呟いた。
(私は…こんなにも変わってしまいましたわ。母さん)
屋敷から出た事によって。
より多くの"終焉"を迎える人と出逢った。
そして……
…其の殆どを、何も出来ぬままに。
(……どうしようも出来ない事が、多すぎる)
哀しい程に。
妹の事だって、そうだった。
あの夜を越えた後、鈴花を二度と親戚の目に入れない事を条件に、鈴花は死から逃れた。
其の後、今の職場である酒場の主人が自分達姉妹の実質的な保護者になってくれた。然し、妹の方は、以前父が治めていた、此の土地では、知れ渡りすぎていた。
家を潰した忌み子。
波打つ琥珀色の髪を持った……深い深い藍色の瞳をした……
…そんな人物は、黒髪黒目が基本的な此の都市国家では、恐らく一人しかいない。
忌み子が居る、という理由で酒場の客が減る可能性もあったので、結局、街はずれ、貴族の屋敷からも酒場からも遠いところにあった、昔、人と馴れ合えず、街から離れて暮らしていた人が遺した家に、私達姉妹は住む事になった。
色々、不便な事もあったけれど、妹の安全には変えられない。
あの子も其れを分かっているのだろうか。時々、何の前触れもなく「御免なさい」と、そう呟いてくる。
あの子は……あの子は、昔と比べたら大分年相応には、なってくれた。
他都市からきた商人から買った"ふりる”というものなので飾った可愛らしい着物や、大きな"りぼん”などに、「可愛い」といって、笑ってくれた。身につけて、「似合うかな?」と訊ねてくれた。
昔は、其れすらしてくれなかった。
唯、唯。
何故自分が生きているのか。
何故自分が生かされているのか。
其れが分からない、といった風にずっとぼんやりと壁を見つめていた。
哀しいくらいに、あの子は何も感じず、唯、自分が生かされている事を疑問に思っていた。
今は、そんな事を表には出さず、笑ってくれている。
けれど、偶に呟く謝罪の言葉は、私の胸を痛めるだけだった。
何故、気付いてくれないのか。
自分は望まれて生きているのだと。
愛されて、此処に居るのだと。
あの子に向けられる視線は、大概、冷たい。
今では家事の殆どをあの子に任せているが、買い物だけはさせていなかった。
…先ず、売ってくれないだろうから。
其れに加えて、暴行などに合う恐れがある。
…其れは、避けなければいけない。
私はあの子の姉で。母なのだ。
守りきる、義務がある。
…そう、だからこそ。
あの子には自分を嫌いになって欲しく、なかった。
私は貴女を愛しているから。
貴女も自分を愛しなさい。
そう、言いたかった。
…いえなかった。
自分に疑問を抱くのは、私もまた、同じなのだから。
街に入り、暫くすると、私は少しだけ、立ち止まった。
今、横を過ぎた人。
其の瞳から見えた……
激しい叫び声。
荒々しい音。
そして――
「――……」
ばっと振り向いたけれど、其の人は、もう見当たらなかった。
私は目を閉じると、直ぐにあけて。何事もなかったかのように歩き出す。
…私は、既にアビリティというものを使いこなせる、魔曲使いとなっていた。
戦う力は、此の身に確かにある。
けれど……けれど。
それでも、どうしようもならない事が、多すぎた。
哀しいくらいに。
多すぎた。
十年の間、私は幾人か私と同じ力を持った人と出逢った。
其れは都市国家から都市国家へと巡る旅人だったり、偶々店の客として着た、此の都市の十人だったりした。
そして私は、自分の力の名前を知った。意味を知った。
エンドブレイカー。
ルーツ。
私のルーツは、イノセント。…先天性の能力。
けれど、知ったところで、私はやはり無力で。
救えない理不尽な終焉から、逃げるようにして私は、妹を育ててきた。
ある意味、あの子を利用しているのかもしれない。
…酷い、姉ね。
其れを、認めざるをえなかった。
東の都市国家らしい形態をしたソードハープを鳴らして、私は歌っていた。
夜に限らず、此の酒場には食事をとりにきたりと、多くの利用者が訪れる。
食事に華を添える程度に、という事で、私は故郷の歌を歌っていた。
指で弦を鳴らし、声で詩を奏でる。
歌は、好き。
だから此の時間は好きだったけれど、故郷を恋いうる、此の曲は実はあまり好きではなかった。
此処には、哀しい思い出が多すぎて。
此処では、私の大切なあの子は生きていけない。
此処では、私達が望む幸せが手に入る事は、ない。
外に出たい。
外に、出たかった。
母さんが昔、優しい目をしながら語ってくれた外の世界へ。
私も、行きたかった。
…けれど、其れは無理なのだろう。
歌い終わり、ゆっくりと頭を下げると、幾人かの人が、拍手をしてくれる。もう一曲、という声が聞こえてきたので、私は其れに答えて微笑み、また、弦に指をあてがう。
此処は、棘には覆われていない。
其の気配がないから。
…私、私は。
外に出られるのならば、棘があるところへ向かいたい。
其処で…哀しい終焉を、壊したい。
けれど、出来ない話だった。
私には妹が居る。
星霊術士になる勉強はしていても、今のところ、何も扱えない妹が。
そして、エンドブレイカーでは無い妹が。
此処で一人で居たら、確実に殺されてしまう妹が……。
連れて行って、あの子が棘によってマスカレイド化する可能性は零では無い。
其れに、もしあの子がマスカレイドと対峙してしまったら?
なす術は、無い。
何より、私はあの子を護らなくてはいけない。
だから、出来なかった。
天井を仰ぐようにして、歌う。
でも、もしかしたら。
…外にいけば、あの子をあの子としてみてくれる人が現れるかもしれない。
あの子を私以上に愛してくれる人が現れて。
あの子の、幸せをつかめるかもしれない。
…けど、其れは。
夢でしか――
声は、天井へと吸い込まれ。
其れ以上、響く事は、無かった。
其の日は、早番だったから、夕方には家に帰れた。
ソードハープをもったまま、私は家路を辿る。
太陽が傾いて、紅い、紅い、柔らかな光を作り出していた。
終焉を叩き潰したい、という思いと。あの子を護らなければならない、という想いと。
重なり合って、結局私は、止まったままだった。
家まで、あと少し。
息を吸った。そして、小さく目を閉じ、開けた。
あの子には、笑顔で接したい。
其れもあったけれど、何より私は家に帰る度に、決意が必要だったから。
…忌み子といわれるあの子が、何時も無事だという保証は…何処にも、なかったから。
家に戻る度に感じる不安を、心に押し込めて。
そして、私は家の前へと立った。
そして、何時もは見ないものを見た。
「…え?」
家の前に植えてある、桜の樹。
枝が侵入し、私達の家の庭に、桜の花弁が落ちていた。
妹が好きな花。
其の、淡い色合いの花弁が堕ち、夕日によって照らされた地に自分を抱きしめて蹲っているのは、
「…鈴!?」
一瞬、頭が真っ白になった。
エンディングは見ていないのに。
何故。
どうして――…
他に人影は、無い。
ソードハープを投げ捨て、妹の傍へと駆け寄ると、妹を、強く抱きしめた。
「鈴、鈴っ…!何が、あったのっ?」
今考えれば、私はかなりパニックになっていた。そんな私の存在に気付いたのか、妹がぼんやりと顔をあげる。其の顔は、意外に落ち着いていた。
「お姉ちゃん…帰ってたんだ。お帰りなさい」
「そんな事よりっ…貴女、どうしたの!?」
静かな口調で言葉を紡ぐ妹に、私は震える声で訊ねる。
「まさか、誰かが――…」
「…光が、」
私が、仮定の一つをあげる前に、妹は、遠くを見るような目で、呟く。
「光と…声が…」
「――……え?」
其の言葉に、私は妹を抱きしめたまま、固まってしまった。
光。
声。
まさか。
まさか――
「天……啓……?」
妹の瞳は、空をぼんやりと眺めている。
然し、小さく、本当に小さく、妹は、頷いた。
「そんな事…言ってた気が…する」
「――…」
何も、いえなかった。
頭が真っ白になった。
其れに対して、何を思ったのか。
自分でも分からない。
けれど、言葉が、私の意志とは関係なしに、口から紡がれていた。
…私達姉妹が、いいえ、此の子が。
忌まれる事無く、暮らせる手段を。
「外に……外に……出ましょう……。…此処にはきっと…何も無いわ…」
自分でも、何を言ってるか分からなかった。
けれど、妹は小さく頷いて。
私を、抱きしめ返してくれた。
