夢を見ていよう。何時か醒める其の時まで。
(TW3「エンドブレイカー!!」で活動しているキャラクターと、その後ろががやがやと活動するところです。
間違えてきてしまった方は、回れ右を推薦します)
カレンダー
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
フリーエリア
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
プロフィール
HN:
後ろのほうに居る人
性別:
非公開
職業:
学生やってます。
趣味:
読書とか。PCとか。ゲームとか←
自己紹介:
====================
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
カウンター
広告
仕事から帰ると、あの子は何時ものように、お帰りなさい、と笑顔で迎えてくれた。
けれど、其の眼が少し腫れているのに、気付いた。気付かない、わけがなかった。
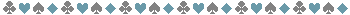
何時ものようにお喋りをしながら、ご飯を食べて、入浴して――
そんな、一通りの事が終わった、夜の本当の短い時間。
「ねぇ、お姉ちゃん」
「・・・なぁに?」
月と、妹が作ってくれたおつまみを肴に清酒を飲んでいると、妹が、いつの間にか私の隣に座っていた。
縁側。
吹き曝しの其処は寒く、こうして御酒を飲む以外に、夜に利用する事は殆ど無い。其れは、本当に昔からだった。
だから、そんな場所に妹が来た事に驚いて、けれど、笑顔で迎える。
「鈴も飲む?」
「馬鹿」
不機嫌そうになった顔を見て、ふふ、と笑って其の琥珀色の髪をなでる。
お母様の髪の色。
そういえば、此の子は成長をするごとにお母様に似てきた――・・・そんな事を思っていると、鈴は私に抱きつく。
「あらあら。甘えん坊さんね。珍しい」
「前は良くしてたでしょー?」
「恋人さんが出来てからは殆ど無かったじゃない?」
「其れは其れー。此れは此れー」
「あらあら、ふふふ。・・・仕様のない子ね」
そうは言いながら、微笑んだ。
そして、ゆっくりと手を伸ばすと、妹の髪をなでる。妹は、嬉しそうに笑った。
其れを見ていると、御酒何かに頼らないでもいい気がした。
・・・の、だけれど。
「お姉ちゃん、最近・・・変」
其の一言に、思わず固まった。
笑顔のまま固まった私を上目遣いで、じっと妹は見る。
其の探るような視線。
幼い頃、本当に周りの全てを嫌っていたあの時に見せていた其の視線に、一瞬、心に何かが走り――そして、其れを押さえつけた。
「そんな事、無いわよ?」
「嘘」
「嘘なんかじゃないわ」
「嘘だよ・・・、だって」
妹は、私に深く抱きつく。
ふと、幼い頃、怖い夢を見て寝付けなかった此の子がこうして抱きついてきてくれた事を思い出して――・・・嗚呼、そんな子がこんなに大きくなったのかな、と思って、寂しくなった。
「私も・・・そうだったもん」
・・・そして、其の言葉が、心に嫌でも響いた。
つい、此の間まで此の子が狂う程に求めていたモノ。
手に入るのに、手に入らなかった曖昧なモノ。
私は・・・私は。
姉として、母として。
此の子を見守るしか、無かった。
そうしている内に、この子は仲間と一緒に其れを乗り切り、そして自分の気持ちも相手の気持ちも、理解した。
・・無論、問題が全て無くなったわけではないが。
人を想う時の柔らかい表情の妹を、私は好きだった。
嬉しくなるのだ。
たった一人の可愛い妹の、其の成長に。
唯。
其の成長が故に、見破られた。
「――・・・」
私は其れでも、笑顔のままで、妹を抱きしめ返した。
ぎゅっと抱きしめると、柔らかい質感と温もりが返って来た。
変わらないもの。其れに、安心して微笑んだまま、瞳を閉じた。
「・・・幸せになってほしいの」
「――・・・・」
紡ぐ。
此れは、私の本当の気持ちだから。
「幸せに、なって欲しいの。・・・だけど、今も縁を切ろうとしないのは私の我侭。
其れでも、幸せになって欲しいの。・・・だって、私は十分すぎるくらい、幸せを貰ったから」
「でも、」
「鈴。・・・私の幸せを決めるのは、貴女では無いわ」
顔を上げた妹に。
だから、其の頭を撫でて、笑いかけた。
「・・・・・・・私よ」
妹が、押し黙った。
其れを見て、私は再度、抱きしめる。
此の子だって・・・今、泣きたいくらいの感情を抱いている筈だ。
人と関わるというのはそういう事。
だから・・・
だから。
「優しい子に、育ってくれたわね。・・・お姉ちゃん、嬉しいわ」
「――・・・・」
答えはない。
其れでも、良かった。
「・・・忘れないでね、」
だけど。
誰にいうでもなく、呟く。
「私は本当に幸せなのよ。もう、十分すぎるくらい、幸せを貰ったわ。・・・だから、私はあの子を不幸にしようとは思わないの。・・・きっと、ね。・・・そうよね」
答えは、無かった。
其れでも、抱きしめ続けていた。
ふと、あの日の夜を思い出して――
そして、全然違う事を、思い出して。
私はあの日よりずっと成長した妹を、唯、唯、抱きしめていた。
PR
この記事にコメントする
