| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
アクスヘイムに向かう途中。
其処で出逢った。
落ち着いた物腰の姉と、臆病な妹。
そんな印象を持たせていた二人に、けれど、もっと感じたのは、
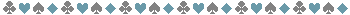
エリザベス・ポターは、読んでいた物語から、眼を上げて窓を見た。
「寒いな……」
今は冬。外では、雪は降っていないが、木枯らしが吹いている。
殆ど裸になった木の枝が、其の度に物悲しそうに揺れている。
もう、落とすものはないよ、と。戸惑うように。
「――…」
彼女は、視線を其処からそらすと、紅茶でも淹れてこよう、と本に栞を挟んで、椅子から立ち上がる。部屋の暖炉には火が入っているが、其れでも寒い。こういう日は、温かいミルクティーでも飲むのが一番だ。
そう思った時、不意に玄関から物音がした。
とんとん、と響く軽やかな音。
来客のようだ。
面倒くさいな、と思いながらも、そう広く無い借家を移動して、玄関まで行き、其の扉を開いて――……
「ふにゃっ」
其の声に、思い切り繭を寄せた。
彼女は、片手で布を被せた皿を抱え、もう片方の手で、ふるふると自分の頭を抑えている。其の白すぎる手の下にある、琥珀色の髪。
ドアに近付きすぎて、ぶつかった――…こんな馬鹿をするのは、知り合いでは一人だけだ。
「何してる?スズ」
「うー、うー」
スズカ・クラハシは涙目になりながら、エリザベスを見上げる。
「肉じゃが、いっぱい作ったんですー。其れで、ベスにおすそ分けしようかなぁって」
「そう。有り難う。ありがたく受け取っておくから、あんたは帰れ。大丈夫、ちゃんと皿は洗って返してやるから」
「うー!!構って下さいよーーー!!」
「……自分で言うのか、此の馬鹿は」
故郷を出てから、初めて知り合った姉妹の、妹の方。
姉とは違い、落ち着きが無く、表情豊かな其の少女は、自分より一つだけとはいえ、年上というのが信じられない程に子どもっぽく、無邪気だった。加えて、寂しがり屋で、姉や――今は、一緒に暮らしている彼女の大切な人が留守の間は、時折こうやって遊びにきている。
また、一人暮らしのエリザベスを気遣って、色々と作っては持ってきてくれる。其れは有り難いし、美味しいのだが、そんな事は口にしない。照れくさいとかではなく、純粋に、“此れ”に礼を言う気にはなれない。
「分かった。構ってあげるから」
「わぁいーv」
嬉しそうにスズカは笑う。呆れながら、中へ入れ、と無言で示すと、彼女はお邪魔しまーす、と控えめに言いながら、部屋へと足を踏み入れた。
(いや、違うな)
ふと、そんな事を思った。
初めて逢った時の彼女は、こんなに無邪気では無かったし、こんなに笑わなかった。
もっと、臆病で。
もっと、
――お姉ちゃんに、近寄らないで。
鋭い声を思い出し、隣に居る無邪気な笑顔を見た。
人は変わるのだな、などとそんな事をぼんやりと思う。
そして、自分はどうなのだろう、とそんな事も、思った。
(姉さま……リリア姉さま……)
――とっくに塞がっている傷が、疼いた。
此の二人に、初めて逢った時、此の二人の依存ぶりに呆れた。
二人は、本当の意味で“二人ぼっち”だった。
本人達さえ、気付かぬくらい。
二人ぼっちだった。
そして気付いた。
自分も、姉に依存していた事に。
――姉を喪った事。
彼女らに会った事で、初めて知った。
姉妹の、姉の方が。
何処となく、姉に似ていたから。
だから――
……けれど、違った。
まったく、違った。
姉の髪は透き通る程の銀で、光そのものだった。
彼女の髪は夜闇を切り取ったような、漆黒の美しさだった。
姉の目は、透き通る程に淡く、明るい緑だった。
彼女の目は、黒と呼んでいい程の、深い深い藍色だった
姉は臆病で、其れでも嘘は吐かなかった。
彼女は大胆で、そして嘘吐きだった。
嗚呼、
思った。
確信した。
姉さまは、もう居ない。
(――…)
もう、あれから大分経つのに、まだこんな事を思い出す何て、ボクは馬鹿だ、と苦笑した。
隣に居る少女は気付いてか、気付いてないのか。
「今日はねー、美味しく出来ましたよー、多分。煮崩れしてないんですよー」
そんな風に言って、笑ってる。
「……あんたの事だから、何かが間違って入ってそうだな?」
「そ、そんな事ないもんっ。ベスの馬鹿っ」
わたわたと、拗ねている彼女を見て、僅かに口元を綻ばせた。
彼女は変わった。
そして、変わっていける。
ボクは……
……ボクだって、大切な人が出来た。
あの頃のボクと、違う。
――其れでも、傷跡は疼く。
姉さま、と心の中で呟いた。
ふとした瞬間に思う。
此の姉妹に、自分を重ねた時に、思う。
思っちゃいけない、と思っても思う。
ボクはまだ、
貴女に捕らわれている。
分かっていても。
もう、嘲笑すら出なかった。
