| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
あの時、姉が流した涙の意味の結局理解できぬまま。
月日だけが流れて、そして、私は其れを迎えた。
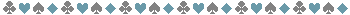
「じゃあ、行ってくるわね。お留守番、宜しくね?」
「ん、行ってらっしゃい、お姉ちゃん。……がんばってね」
姉が微笑んで、私の髪を撫でて、そして引き戸をがらがらと開けて、其の外へ出て行く。
最後にもう一度微笑んで、ぴしゃん、と小さな音をたてて、其の戸は閉じられた。
「――…お洗濯、しよ」
其れを見届け、暫くしてから、ぼんやりと呟いた。
あれから、十年。
姉は酒場で歌ったり、配膳をしたりして私を育ててくれた。
姉は詳しくは話さなかったけれど、きっと其処は母が昔働いて、父と出逢った酒場だったのだと思う。だから、私達のような没落貴族を迎えてくれた……のだと思う。此の家も、其処の主人が快く貸してくれた、借家だった。
……お姉ちゃんが無理しなければ、私はそんな事どうでもよかったのだけれど。
そして、私は。
此の十年間、殆ど外へ出なかった。
お洗濯など、どうしても出なければいけない時をのぞいて、私は家の中に居た。
家事は私の担当だったが、お買い物は私はしなかった。
此の十年間、たまに家を訪ねてくる人を除いては、私は姉以外の人とかかわりを持っていない。
……多分、其れが忌み子であった私を生かしておく条件だったのだと思う。
二度と、彼らの目に触れない事。
姉は言わなかったけれど、何となく理解はしてた。
だって、姉が留守の時、此処を訪ねてくる人は明らかに私に脅えていたし、……嫌そうな目で私を見て、直ぐに逃げ出したから。
哀しいとは思わなかった。
寂しいとは思わなかった。
お姉ちゃんが居てくれたから。
お姉ちゃんが私を護ってくれたから。
だから、私は安心して暮らせた。
目立つ髪色と目の色の所為で、姉に楽をさせる為に働きにいく事も出来なかったのがもどかしかったけれど、其れでも姉が私の作った料理を「美味しい」といって食べてくれると、それだけで幸せだった。
他には何も、要らなかった。
「――…中々、」
一通りの家事が終わった後、私は描いた其れを見て、軽くため息をつく。
星霊スピカ。
星霊術士として、召喚できる最初の星霊。
何時からか、私は星霊術士としての勉強を始めていた。
姉が、魔曲使いとしての才能を開花したから、其れを見て、慌てたのかもしれない。
お姉ちゃんを護れない、って。
……何はともあれ、私は時間さえあれば、其の勉強をしていたし、時間は山ほどあった。家から出ないのなら、当然だけれど。
「うーん」
思うように伸びず、ふぅ、とため息をついた。
「私、お姉ちゃんの妹なのにな」
ぽつり、と呟いた。
何をしても、天才的に才能を発揮する姉に、僅かながらも私は劣等感を抱いていた。
けれど、其れを自身に感じると、私はまた自己嫌悪にかられる。
大切な姉を、そんな風に感じるなんて、どうかしてる、と。
「――……」
ふと、縁側の方を向いた。
申し訳程度の庭。
其の先にある、小さな桜の樹。
時期は、春だった。
だから、少し離れた此処から見ても、舞い散る花弁が見えて、綺麗だった。
ひらひら。
ふわり、ひら。
踊るように、舞うように。
其れでも、散って堕ちていく花弁を、じっと見つめていた。
遠くから、一枚一枚を見ると、まるで純白の花弁で。
そんな淡い色に、私は見惚れた。
毎年、姉の誕生日の近くに咲く此の花を、私は愛していた。
そういえば、生家にも桜の樹はあったけれど、此処程綺麗ではなかったと思う。
……あまり、真面目に見た事が無いからわからないけれど。
私は半分無意識に立ち上がり、縁側から突っ掛けを履いて外へ出ていた。
外には人通りは居ない。
人目に触れる事は、無いだろう。
当時、私は姉に習って舞を教わっていたから、あの桜の花弁と共に舞いたい気持ちがあった。
だから、ゆっくりと近付き、そして其の満開の花弁の下に立つ。
ひらり、ひら。
ふわり、ひら。
淡いピンクの花弁は、風が吹く度にはがれると、ひとひらの純白の花弁に変わる。
「綺麗――……」
感嘆のため息をもらして、私はほぼ無意識に横髪のリボンに触れていた。
――ほら、可愛いでしょう?
姉がそういって笑って、酒場に出入りする行商人から買ってきてくれたもの。
自分の為に使うお金をぎりぎりまで削って、私に買ってきてくれた、桜色のレースのリボン。
私の宝物だった。
舞い散る花弁と同じ色をしたリボンに触れながら、もっと近くで見ようと、私は樹に更に近付いた。
刹那、
「!!?」
何の、前触れもなかった。
突然、視界が光に覆われて、そして、
――……
其の"声"がやみ、光が消えた時。
私は眩い光に眩んだ片目を抑えて、蹲っていた。
「何、何なのっ……?」
滑稽な程、脅えていた。
けれど、其の問いに対する答えは何処にもなく。
唯、舞い散る桜の下で、私はそうしていた。
