夢を見ていよう。何時か醒める其の時まで。
(TW3「エンドブレイカー!!」で活動しているキャラクターと、その後ろががやがやと活動するところです。
間違えてきてしまった方は、回れ右を推薦します)
カレンダー
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
フリーエリア
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
プロフィール
HN:
後ろのほうに居る人
性別:
非公開
職業:
学生やってます。
趣味:
読書とか。PCとか。ゲームとか←
自己紹介:
====================
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
このブログのイラストは、株式会社トミーウォーカーのPBW『TW1:無限のファンタジア』『TW3:
エンドブレイカー』用のイラストとして、背後が作成を依頼したものです。
イラストの使用権は発注した背後に、著作権はイラストマスターに、全ての権利は株式会社トミーウォーカーが所有します。
=====================
カウンター
広告
何時もの部屋。
何時もと違う風景。
横たわるあの子。
ううん、あの子とも分からない。
其れくらいに斬られ続けた――・・・・
其れが、私があの子の瞳から見た、あの子の"終焉”だった。
――・・・そして、もう一つ。
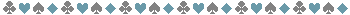
真夜中。
私は必死の思いで起きていた。
幼い為か、激しい睡魔が私を襲ったが、今はそんな事に構っている場合ではなかった。
数日前――・・・
何時ものように妹と遊んでいると、あの子の瞳から見えたのだ。
そう、――"終焉”。
私が誰にも言う事の出来ない、此の力で。
私はあの子の終わりを、しかと見た。
そして其れは、あまりに激しいものだった。
三人の男。
――叔父達だった。
彼らが持つ、刀。
全てが夜闇の中でもはっきり、其れと分かる程に紅く輝いていた。
其の紅の根源となった妹は――
「・・・・っ!!」
あんな哀しい終焉を、妹に迎えさせるわけにはいかなかった。
私は妹への想いだけをしっかりと抱えたまま、足音を忍ばせて自分の部屋から出た。
あの時の光景を浮かべるのなら、きっとあれは夜。
其れも深夜。あの子の部屋での出来事に間違いが無い。
最初はゆっくり歩いていたが、やがて耐え切れず、走った。
脳裏に、今までこうやって、救えなかった人達の姿が浮かんで、消えた。
己の無力を呪った。
華道や、茶道に長けていても。
楽器を演奏出来ても、歌が歌えても。
(何も救えないんじゃあ、意味がない――・・・!!)
泣きたい気持ちで、走る。走る。
時折、足が縺れそうになったが、其れでも転びもせずに、走る。
あの子の部屋は、私達家族が生活する棟とは違う棟にある。
急がなくては――・・・
「――・・・若葉?」
呼び止められた、其の声に。
私は思わず、ぎくりと身体を固くさせ、そして廊下から見える、中庭へと眼を向けた。
其処に、居たのは。
「お父様・・・お母様・・・」
――あの子が殺されてしまうのが、確定だと思った理由はもう一つ。
私は、見ていたのだ。
そう――・・・
父と母は、深夜にも関わらず、外へ出る為の格好をし、大きな荷物を持っていた。
(今日・・・だったのね)
そんな事を思い、思わず一歩退いた。
そして、信じたくなかった事の確定に、涙が出そうになった。
「若葉、どうしたの?・・・こんな夜更けに」
母が、静かに声を掛けて来る。
「・・・部屋に戻りなさい、若葉」
父が、強い口調で言った。――然し、其の口調も、そして其の顔も、疲れきっているのを、私は見逃さなかった。
「・・・お断りします」
だから、答えた。
哀しかった、けれど。
「あの子を・・・自分達の娘を売って、逃走しようとする、貴方達の言う事は、聞きたくありません」
「――・・・!!??」
私が見た、もう一つの"終焉"。
其れは、此の家の終わりだった。
「お父様、下手に領土を広げようとするからですわ。・・・そんな大人の勝手に、あの子を使う何て・・・許せません」
「・・・若葉、お前・・・!?」
狼狽した父が、ぱくぱくとまるで、金魚のように口を動かす。最初の言葉以外、彼の口からは何も出なかったけれど。
可笑しくて笑った。
・・・哀しくて、笑った。
「貴方達が仰った、忌み子はあの子ではありませんわ」
自分の胸に、手を当てて。
笑う。嗤う。
嗤うしか、無かった。
「――私、です」
――空気が、凍った。
私は、もう早く此処から去りたかった。
貴族の栄光にしか護られてなかった父に興味は無かった。一人の人間としては何も出来なかった、そして貴族としての誇りも父親としての愛情も殆ど何も無かった父に興味は無かった。
そして、あの子を見捨てる母にも、興味が無かった。
けれど。
「・・・若葉」
母が、苦しそうな顔をして、一歩前へ出た。私は反射的に、一歩退く。
母は其れを哀しそうに見た後に、彼女の夫へという。
「先へ行っていて。あなた」
「然し・・・」
「良いから!!」
激しい口調に押されて、父が駆けて行った。門の方へ。
私が其れを呆れながら見送っていると、母は私に近付いてきた。逃げようとする私を、其の前に強く抱き寄せる。・・・何時も、こうしてくれるのと変わらぬ温もりだった。
「・・・若葉、良くお聞きなさい」
そして、私の耳元で、囁くように母は言う。
「私は、旅の途中で終焉を終焉する者、という人の話を聞いた事があるわ」
「・・・っ!」
「きっと、貴女はそうなのね。・・・何となくだけど、そう思っていたわ。ほら、事故死した女中さん・・・覚えている?・・・貴女は、彼女をじっと見ていた。知っていたのね。そうなんでしょう?」
「・・・私、は・・・」
「力が無い何て、無いわ。・・・貴女はまだ幼いのよ。仕方が無いわ。・・・でも、其れを知っていて、こんな事を頼む、母を赦してね」
母は、私を少し引き離した。
そして、其の顔を見て、私は黙るしか、無かった。
母は、泣いていた。月明かりに照らされて、綺麗に泣いていたのだ。
「あの子・・・鈴花を。護ってあげて。・・・私には出来ない。私がそうすると、きっとあの人が殺される・・・。・・・御免なさい、御免なさい。私は夫も娘達も、喪いたくは無かった・・・」
「おかあ、さま?」
「きっと、今ならまだ間に合う・・・。彼らは貴女・・・幸を運ぶといわれた貴女に手出しはしない・・・。若葉・・・もし彼らの恩恵を受けるのが嫌なら、私が過去、働いていた酒場に行きなさい・・・。話はつけてあるわ。地図も・・・おいていったから」
「お母様!!」
思わず、強く叫んだ。
どうすればいいのか、分からなかった。
分からなくて、泣いた。泣いていた。
情けないくらいに、涙が出ていた。
私達を見捨てるだけだと思っていたのに、其処に居たのは、何時もの私が愛して尊敬する、母だったのだから。
母は、私を強く抱きしめた。
「あの子には、伝えないで。あの子には、私達を恨ませて。そうすれば、きっとあの子は自分を愛せる。
ねぇ、若葉――」
――庭に咲いていた、桜がふわり、と散った。
ふと、何年か前にこっそりと母と妹といった、花見を思い出した。
あの時は、三人で笑った。
そして其れの、最後だった。
「若葉、貴女も。鈴花も・・・私は愛しているわ。
私の可愛い、娘達――・・・。生きていれば・・・きっと、また逢えるわ」
耳に響いた、幻のような、声。
其れを終えた瞬間――・・・母は、私を離して、そして走っていった。
そして、私も走った。
「やめてぇええぇえええぇええ!!!!!」
そして。
壊した終焉、其の先を生きれるあの子を抱きしめて。
泣いた。
唯、泣いた。
哀しくて。
悔しくて。
愛する人を喪って。
二度と逢えないのを知って。
そして。
・・・此の子が、生きていてくれる事。
其の喜び。
全てがあわさって、泣いた。
桜は、空高く舞う事など無く、唯、唯、堕ちては私達を、見守っていた。
PR
この記事にコメントする
